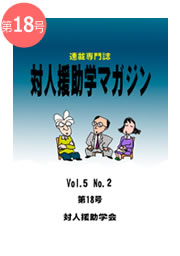
A4/235ページ
発行日 2014年9月15日
発行者 対人援助学会
編集長 団 士郎
【編集長から】
新しい執筆者を募って書いていただく。長年の執筆者にも、書きたいことのある限り書いていただく。
マガジンがドンドン厚くなるのは構わない。それはWeb 雑誌の利点だ。誰も読み切れないほど分厚くなったとしても、バックナンバーが揃っている限りいつも、何処かの、誰かにとって貴重な資料になるはずだ。
しかし人の気力も、命にも限りはあるのだから、勇退されることはさまたげない。それが結果的に世代交代になっている形も想定内だ。
上世代が突然に引退を口にして譲ろうとしたり、下世代がポジションの交代を要求したりしているところに、本当の意味での継承、交代は起こらないのではないかと思う。長寿社会に於ける智の併走こそ、あるべき姿なのではないか。
支払いや、掲載条件を云々しなくてもよいツールが手に入ったことで、そういう従来の作法から、私達が自由になったのだ。掲載分量や回数を区切らなければならないと思ってしまうのは、旧来型の発想だ。この事は、もっときちんと考えておく必要がある。
死ぬまで現役の方も、新たな気持ちで再登場の方も歓迎である。是非、意欲的なエントリーをどうぞ。ロングアンドワインディングロードである。みんなで成果を築いていこうではありませんか。
| 対人援助学マガジン 第18号 | |
|---|---|
| ■全ページ(235ページ) | |
| ■各ページ(執筆者) | |
| 表紙 | |
| 目次 | |
| ・in the shadow of the family tree 「Doors」 | Shiro Dan |
| ・執筆者@短信 | 執筆者全員 |
| ・知的障害者の労働現場 18 | 千葉 晃央 |
| ・臨床社会学の方法(6) | 中村 正 |
| ・ケアマネだからできること | 木村 晃子 |
| ・街場の就活論 vol.18 | 団 遊 |
| ・コミュニティを探して (8) | 藤 信子 |
| ・映画の中の子どもたち18「ファイ」 | 川崎 二三彦 |
| ・子どもと家族と学校と(開業カウンセラー日誌) 18 | 中島 弘美 |
| ・蟷螂の斧part 2 トークライブ2001第3回 | 団 士郎 |
| ・学校臨床の新展開
17 |
浦田 雅夫 |
| ・学びの森の住人たち(13) | 北村 真也 |
| ・幼稚園の現場から18 | 鶴谷 主一 |
| ・福祉系対人援助職養成の現場から 18 | 西川 友理 |
| ・先人と知恵から(6) | 河岸 由里子 |
| ・生殖医療と家族援助(3) | 荒木 晃子 |
| ・対人援助学&心理学の縦横無尽 15 | サトウタツヤ |
| ・ドラマセラピーの手法(7) | 尾上 明代 |
| ・日本のジェノグラム(5) | 早樫 一男 |
| ・きもちは言葉をさがしている 第17話 | 水野 スウ |
| ・やくしまに暮らして 第十七章 | 大野 睦 |
| ・お寺の社会性(十六)―生臭坊主のつぶやきー | 竹中 尚文 |
| ・これからの男性援助を考える 第十六回 | 坊 隆史・松本 健輔 |
| ・ノーサイド 第14回 禍害と被害を超えた論理の構築 | 中村 周平 |
| ・男は痛い!第12回「テルマエ・ロマエ」 | 國友 万裕 |
| ・援助職のリカバリー(11) | 袴田 洋子 |
| ・周旋家日記(11) | 乾 明紀 |
| ・トランスジェンダーをいきる(10) | 牛若 孝治 |
| ・役場の対人援助論(10) | 岡崎 正明 |
| ・新版K式発達検査をめぐって(その9) | 大谷 多加志 |
| ・十代の母という生き方(8) | 大川 聡子 |
| ・電脳援助(8) | 浅田 英輔 |
| ・日曜寺子屋家族塾の取り組み7 | 古川 秀明 |
| ・Journey to my PhD @ York in イギリス/Vol.6 | 浅野 貴博 |
| ・養育里親~もうひとつの家族~ 6 | 坂口 伊都 |
| ・周辺からの記憶4 | 村本 邦子 |
| ・病児保育奮闘記(3) | 大石 仁美 |
| ・新連載 ラホヤ村通信 (1) | 高垣 愉佳 |
| ・新連載 ハチドリの器 | 見野 大介 |
| ・編集後記 | 編集長&編集員 |
