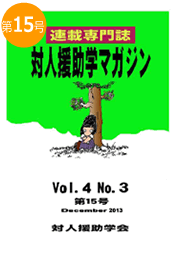
A4/243ページ
発行日 2013年12月15日
発行者 対人援助学会
編集長 団 士郎
【編集長から】
■学会員200人ほどのちいさな組織ながら、『学会誌』、『対人援助学マガジン』、年次大会、定例研修会と、いろんな事が小さく継続実施できている。
会員のスタンスも様々だが、継続というところで連携できているからこその事態なのだろう。会員拡大にあまり積極的ではないのも、大きくなるのが良いことだとは思っていないからかもしれない。(基本的に入会希望は大歓迎です。事務局にお知らせ下さい。)
「学会誌」もこの「マガジン」も、会員以外の人たちにも無料で読んでいただけるスタイルをとっている。学会員であることの特権はこれらに執筆する権利と学会で発表する権利くらいである。ならば書く気や発表する気のない人は学会員にならなくてもいい。学会費を払うメリットがないじゃないかとおっしゃればそうかも知れない。
しかし、そこが対人援助学の理念、「融合と連携」を考えたときには違っている。
学会員になると、対人援助学会の維持継続や、更には対人援助学フィールドの継続発展に、ささやかながらも経済的貢献をしていることになる。
利用者や消費者ではなく、参加者、構成員になってこの世の中とコンタクトできる事になる。そのエントリー料が学会費である。
私達は今、安いほど良い、タダならもっと良いという世界ではなく、意味あることに賛同の一票としてお札を出す習慣を持たなければならない。
誰かがやってくれるだろうと思っている内に、崩れて消えてしまう世界にしないために、維持構成員として出費を引き受けなければならない。これが良きお金の使い方というものだろう。
| 対人援助学マガジン 第15号 | |
|---|---|
| ■全ページ(243ページ) | |
| ■各ページ(執筆者) | |
| 表紙 | |
| 目次 | |
| ・執筆者@短信 | 執筆者全員 |
| ・知的障害者の労働現場 015 | 千葉 晃央 |
| ・臨床社会学の方法(3) | 中村 正 |
| ・ケアマネだからできること | 木村 晃子 |
| ・街場の就活論 vol.15「まだ、大丈夫」 | 団 遊 |
| ・コミュニティを探して (5) | 藤 信子 |
| ・第15回誌上ひとりワークショップ | 岡田 隆介 |
| ・映画の中の子どもたち15「もうひとりの息子」 | 川崎 二三彦 |
| ・子どもと家族と学校と(開業カウンセラー日誌) 15 | 中島 弘美 |
| ・蟷螂の斧part 2 様々なシステムと私 第2回 | 団 士郎 |
| ・学校臨床の新展開 (15) | 浦田 雅夫 |
| ・学びの森の住人たち(10) | 北村 真也 |
| ・幼稚園の現場からⅩV | 鶴谷 主一 |
| ・福祉系対人援助職養成の現場から (15) | 西川 友理 |
| ・先人と知恵から(3) | 河岸 由里子 |
| ・不妊治療現場の過去・現在・未来 最終章 | 荒木 晃子 |
| ・対人援助学&心理学の縦横無尽 (12) | サトウタツヤ |
| ・ドラマセラピーの手法(5) | 尾上 明代 |
| ・日本のジェノグラム(2) | 早樫 一男 |
| ・きもちは言葉をさがしている 第14話 | 水野 スウ |
| ・やくしまに暮らして 第十四章 | 大野 睦 |
| ・お寺の社会性(十三)―生臭坊主のつぶやきー | 竹中 尚文 |
| ・これからの男性援助を考える 第十三回 | 坊 隆史 |
| ・ノーサイド 第11回 禍害と被害を超えた論理の構築 | 中村 周平 |
| ・それでも「遍照金剛言う」ことにします(10) | 三野 宏治 |
| ・男は痛い!第9回「HK/変態仮面」 | 國友 万裕 |
| ・援助職のリカバリー(8) | 袴田 洋子 |
| ・周旋家日記(8) | 乾 明紀 |
| ・トランスジェンダーをいきる(7) | 牛若 孝治 |
| ・役場の対人援助論(7) | 岡崎 正明 |
| ・新版K式発達検査をめぐって(その6) | 大谷 多加志 |
| ・十代の母という生き方(5) | 大川 聡子 |
| ・電脳援助(5) | 浅田 英輔 |
| ・日曜寺子屋家族塾の取り組み4 | 古川 秀明 |
| ・Journey to my PhD @ York in イギリス/Vol.3 | 浅野 貴博 |
| ・養育里親~もうひとつの家族~ 3 | 坂口 伊都 |
| ・新連載周辺からの記憶1 | 村本 邦子 |
| ・誌上再現企画ワークショップ「対人援助マガジンを考える」 | 第五回大会企画 |
| ・印刷製本版の作り方 | 団士郎 |
| ・編集後記 | 編集長&編集員 |
