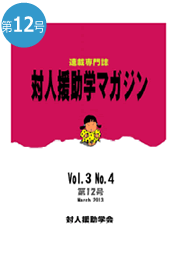
A4/246ページ
発行日 2013年3月15日
発行者 対人援助学会
編集長 団 士郎
【編集長から】
■創刊丸三年が経った。年四回、三年で十二号。ますます読み切るのが難しいボリュームの雑誌になってきている。
これは意図通りなので何の問題もない。繰り返し書いているように、このWeb 雑誌は対人援助領域のこの時代の資料庫になればよい。
現場の日常はドンドン過ぎ去る時間の渦である。忘却も半端ではない。覚えておきたいと思ったことさえ、忘却の彼方に去ってゆく。
成功も失敗も、喜びも後悔も皆、忘却の対象になる。何度過ちを繰り返したら学ぶのだろう・・・は愚問である。何度繰り返しても、人は忘れるのである。だから記録が大切なのだ。いや、記録されたものだけが記憶(歴史)になるのである。
当然のことながら資料は記述した者がいる。だから主観である。渦中の記録であるところに嘘はないが、当事者としての思い込みはある。
しかしこれは忘れてしまいたいという意図に基づいた隠蔽や、改ざんとは一線を画している。風化を待つ無自覚な悪意に対抗できるのは、それを阻止する装置である。
■マガジンとしての面白さ、これも大きなテーマである。なにを面白く感じるかは個人の嗜好なので、多様な誌面展開をするのが妥当なところだ。
ページの拡張が問題にならないWeb版だから、一冊の中に複数の雑誌が同居しているような感覚もありである。と、こう書いていたところに、一番遅れた原稿が届いて仰天した。45ページある。ゆっくり読ませていただきますサトウタツヤさん。
このマガジンは出来るだけ多様に展開したいと願っている。思いのある方からの、連載希望はいつでも受け付けています。編集長にお問い合わせ下さい。
| 対人援助学マガジン 第12号 | |
|---|---|
| ■全ページ(246ページ) | |
| ■各ページ(執筆者) | |
| 表紙 | |
| 目次 | |
| ・執筆者@短信 | 執筆者全員 |
| ・知的障害者の労働現場 012 | 千葉 晃央 |
| ・社会臨床の視界(12) | 中村 正 |
| ・ケアマネだからできること ~地域とつなぐ~ 連載12 | 木村 晃子 |
| ・街場の就活論 vol.12 | 団 遊 |
| ・コミュニティを探して (2) | 藤 信子 |
| ・第12回誌上ひとりワークショップ | 岡田 隆介 |
| ・第12回 明日の空の向こうに -子どもは未来である- | 川崎 二三彦 |
| ・子どもと家族と学校と (12) | 中島 弘美 |
| ・蟷螂の斧(とうろうのおの)-社会システム変化への介入 第12回 | 団 士郎 |
| ・学校臨床の新展開 (12) | 浦田 雅夫 |
| ・学びの森の住人たち(7) | 北村 真也 |
| ・幼稚園の現場から XII | 鶴谷 主一 |
| ・福祉系対人援助職養成の現場から (12) | 西川 友理 |
| ・我流子育て支援論 (12) | 河岸 由里子 |
| ・不妊治療現場の過去・現在・未来 12 | 荒木 晃子 |
| ・対人援助学&心理学の縦横無尽 (9) | サトウタツヤ |
| ・ドラマセラピーの手法(3) | 尾上 明代 |
| ・家族造形法の深度 (12) | 早樫 一男 |
| ・きもちは言葉をさがしている 第11話 | 水野 スウ |
| ・やくしまに暮らして 第十一章 | 大野 睦 |
| ・お寺の社会性(十)―生臭坊主のつぶやきー | 竹中 尚文 |
| ・こころ日記 ぼちぼち(6) (中学生日記) | 脇野 千恵 |
| ・これからの男性援助を考える 第十回 | 松本 健輔 |
| ・ノーサイド 第8回 禍害と被害を超えた論理の構築 | 中村 周平 |
| ・それでも「遍照金剛言う」ことにします(7) | 三野 宏治 |
| ・「ほほえみの地域づくり」の泣き笑い(7) | 山本 菜穂子 |
| ・男は痛い!第六回 「僕達急行 A列車で行こう」 | 國友 万裕 |
| ・援助職のリカバリー(5) | 袴田 洋子 |
| ・周旋屋日記(5) | 乾明紀 |
| ・トランスジェンダーをいきる(4) | 牛若 孝治 |
| ・役場の対人援助論(4) | 岡崎 正明 |
| ・新版K式発達検査をめぐって(その3) | 大谷 多加志 |
| ・十代の母という生き方(2) | 大川 聡子 |
| ・電脳援助(2) | 浅田 英輔 |
| ・新連載日曜寺子屋家族塾の取り組み1 | 古川 秀明 |
| ・編集後記 | 編集長&編集員 |
